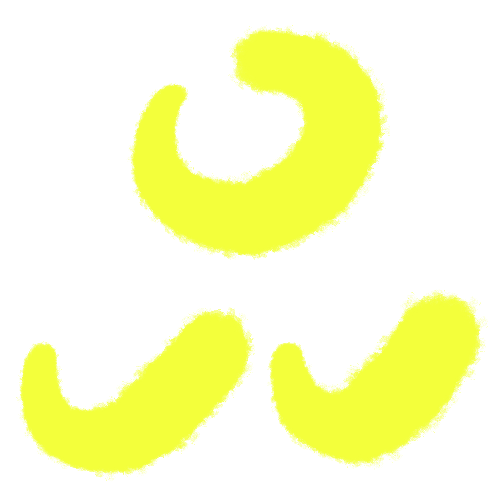子どもの頃にもどりたい?
目の前に魔法使いが現れ、こんな願いを叶えると告げます。「時を戻し、子どもの頃にかえしてさしあげます」
あなたなら、この話にのりますか?
「わー では8歳の頃に戻してください!」
わたしの返答は「とんでもない!やっとおとなになれて幸せなのに、子ども時代に逆戻りなんて!」です。
なぜなら、「自由」を感じるから。
大好きなイチゴを3パック一度に平らげようとも、食事や、お風呂や、寝るタイミングも自由!
イヤなことを有無を言わさずやらなくてもいい。
「やりなさい!」「やらないと〇〇だよ」なんて、おとな達から圧力をかけられることもない。
この自由に気付いたのは、体育の授業で大っ嫌いな長距離走をしなくてもよい、と発見した時。例えば、偽りの腹痛をうったえ〈体育の授業、1時間見学の権利〉を得なくともよいのだ。
「自由」なのはおとな?こども?
ここでの「自由」とは、「やりたいことを、やりたい時にできること。他の存在からの強制や拘束がないこと」を意味する。わがままや横暴とは異なることを明記したい。
どちらかといえば放任主義の親のもとに育った自分から見ても、
子ども時代は自分で決められない項目がおとなのそれよりもずっと多いと感じます。
例えば、
- 食事の量、タイミング、回数
→おとなは1日二食だって、少しずつ6回に分けて食べたって、本人が快適なスタイルでOK!
昼食をたらふく食べたら夕食は軽め、だって自由自在。朝昼晩の1日3回とは誰が決めたんだ? - 触っていいもの、ダメなもの
→おとなは自分が超人になったという自己暗示のもと、興味本位で火にかけたフライパンに触れようが自由。
その結果火傷をしようが自己責任。(火傷をしたら程度に合わせた適切なケアを。ひどくなければ流水で15分ほど冷やしましょう。決して氷や保冷剤で冷やさぬよう) - 学校給食のときの飲料は牛乳のみ(アレルギーや乳糖不耐症でなければ)
→おとなはお水でも、温かいお茶でも好きなものが飲める!
給食の牛乳と白米の組み合わせ、イヤだったな〜〜 - 寝る時間
→おとなは連続ドラマ、シーズン6まで一気観して睡眠時間ゼロだろうが自由。
次の日、睡眠不足でどうなっても自己責任。
いつになったら、これらの自由は許されるのかな?
おとなになるまで待たなければならないことなのか?
じゃあ、「おとな」になるタイミングっていつ?
定義すら法律や文化・風習により大きな幅がある。
「子どものため」は誰のため?
産まれて間もない赤ん坊は、周囲の保護なくしては数日間も生きてゆけません。ひとりではできなかったことも一つ一つ乗り越え、できることが増えてゆく様子を見て成長を感じる。
将来は立派に自立してほしいと願いつつもいざ自立の時が来ると、少し淋しいような、いつまでも守ってあげたいような。よちよちとキッチンに近づけば火元や刃物から離してやり、木の葉が色づく肌寒い日には厚めの服を着せてやる。
成長するにつれ、おとなの助けが不要になってくるが、そこにわかりやすい境目なんてない。
夜も22時をまわれば「早く寝なさい」というのも、成長期のこの子を想ってこそ。
家族揃って食卓につくのを拒否すれば「ああ、学校では集団生活を送れているだろうか」と気をもむ。
進路で迷っているならばアドバイスを与え、導いてやりたい。「お父さんは地元の高校がいいと思うぞ」なんて。
けれど、良かれと思い決定や選択をしてあげるのは、時にその子自身の自己決定・自己選択の機会を奪ってはいないだろうか。自分で考える力まで奪ってしまってはいないだろうか。
考えることができるのは、本人だけ。
感じることができるのは、本人だけ。
代わりになれる者はいない。
「子どものため」と動かすその手は、時に「わたしは、あなたには自分でできる能力はないと思っている」というメッセージとなることがある。
先回りして何か言いたくなっても、すこし見守る。
よりよいガイドの形があるか考えたい。
では、いつ手を差し伸べるべきか?
それは、本人が求めたとき。ではないだろうか。
「あなたが求めればサポートをする準備がある」と、コミュニケーションしておくのも大事だろう。
自由と選択を尊重
みんなが子どもの頃から安心し自由でいられたら、より多くを自分で選択・決定できるなら、どんな世の中になるだろうか。
社会の皆をお互いの自由と選択を尊重し、それぞれが自分自身でいる。
わたしはそんな世界のヴィジョンを見ています。
魔法使いが返答を待っている。
「さあ、子どもの頃にもどりますか?」
どう、答えよう。
その理由はなんだろう。